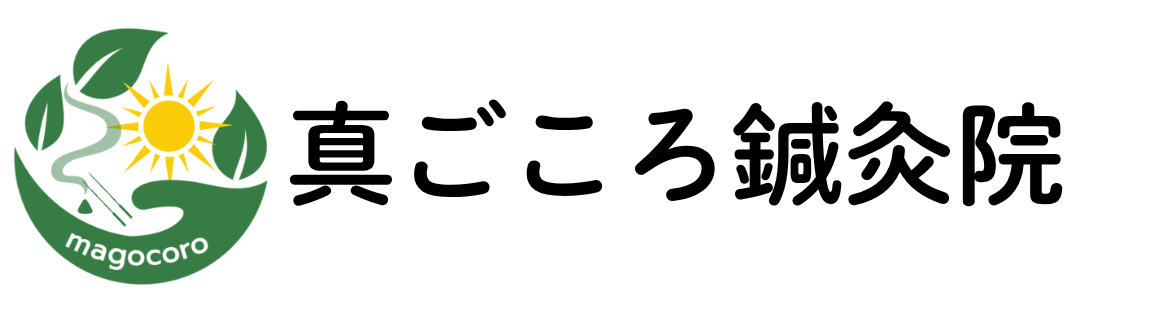こんなお悩みは
ありませんか?
潰瘍性大腸炎とは?
潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)とは、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気です。炎症によって、粘膜がただれて潰瘍(かいよう)をつくり、下痢や血便、腹痛などの症状を引き起こします。
症状がよくなったり(寛解)悪くなったり(再燃)を繰り返す慢性の病気で、厚生労働省が指定する指定難病の一つです。
主な症状
- 下痢(1日に何度もトイレに行く)
- 血便(便に血が混じる)
- 腹痛・腹部の張り
- 発熱、倦怠感
- 体重減少、貧血 など
原因
はっきりとした原因はまだ分かっていませんが、
次のような要因が関係していると考えられています。
- 免疫の異常(自分の腸を攻撃してしまう自己免疫反応)
- ストレスや精神的負担
- 腸内環境の乱れ
- 食生活の欧米化
- 遺伝的な体質
病院でよくある対応
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が起こる病気です。
病院では主に炎症を抑えることを目的に、
5-ASA製剤・ステロイド・免疫抑制剤・生物学的製剤などが使われます。
薬によって炎症を鎮め、症状(下痢・血便・腹痛)を落ち着かせることはできますが、
しばらくすると再燃(再発)してしまうケースも多く見られます。
定期的な内視鏡検査や通院、食事制限、服薬の継続が必要になり、
「いつ再発するかわからない」という不安を抱えながら生活している方も少なくありません。
なぜ病院では改善できないのか?
病院での治療は、炎症という「結果」を抑える治療です。
しかし、炎症を起こす原因の
- 免疫の過剰反応
- 自律神経やストレスの影響
- 腸の働きを支える「気血水(きけつすい)」の乱れ
- 食生活や生活リズムの不調
といった体のバランスの崩れまでは十分に整えられないことがあります。
つまり、「炎症を鎮めるだけ」では、根本の体質や内臓の働きが回復していないため、再び症状がぶり返してしまうのです。
東洋医学とは?
東洋医学は、体を「部分」ではなく「全体」でとらえる医学です。
症状のある腸だけを見るのではなく、
腸の働きを支える五臓六腑のバランス(特に脾・肝・腎)、
そして心(ストレス)と体の関係を重視します。
東洋医学では、同じ「潰瘍性大腸炎」という診断でも、
その原因や体質は人によって異なります。
ですから、一人ひとりの体質を見極めて「内側から整える治療」を行います。
潰瘍性大腸炎になりやすい
3つのタイプ
脾虚(ひきょ)タイプ
消化吸収を司る「脾(=胃腸機能)」が弱っているタイプ。
- 下痢しやすい
- 食後にお腹が張る
- 倦怠感
- 冷え性
- 顔色が悪い
などの不調が起こりやすいことが特徴です。
食生活の乱れや疲労の蓄積が原因となりやすいです。
肝気鬱結(かんきうっけつ)タイプ
ストレスや緊張で「肝(かん)」のエネルギーが滞るタイプ。
- お腹の張り
- ガスが多い
- イライラしやすい
- 不安感
- 症状がストレスで悪化する
などの不調が起こりやすいことが特徴です。
自律神経の乱れが腸に影響を与えています。
腎虚(じんきょ)タイプ
体の根本のエネルギー(生命力)が弱っているタイプ。
- 長年症状を繰り返す
- 下半身の冷え
- 腰のだるさ
- 夜間のトイレ
- 疲れやすさ
などの不調が起こりやすいことが特徴です。
長期的な病気・加齢・過労が関係します。
東洋医学的なアプローチ
鍼灸治療では、腸の炎症を直接抑えるのではなく、体全体のバランスを整えることで、腸の働きを自然に回復させていきます。
鍼灸治療で出来ること
- 自律神経の安定(ストレスに強い体へ)
- 胃腸機能の回復(「脾」を整える)
- 免疫バランスの正常化(「肝」「腎」を整える)
- 冷え・血流の改善
主なツボ例
- 足三里(あしさんり):胃腸を整え、体力を補う
- 太衝(たいしょう):ストレスを緩める
- 気海(きかい):エネルギーを補う
継続していくことで、「再発しにくい体」へと少しずつ変わっていきます。
まとめ
潰瘍性大腸炎は、薬で一時的に炎症を抑えることはできますが、
体の根本的なバランス(気・血・水)の乱れを整えなければ、再発を防ぐことは難しい病気です。
東洋医学では、腸だけでなく「心」と「体」の両面からアプローチし、
本来の自然治癒力を引き出します。
長く続く不調や再燃を繰り返している方は、
ぜひ一度「体質から整える鍼灸治療」を検討してみて下さい。
実際に潰瘍性大腸炎が改善した例

お問合せ・ご予約
当院は完全予約制です。
ご予約は公式LINE, しんきゅうコンパス, お問い合わせフォーム, お電話にて承っております。
お問い合わせはお問い合わせフォーム, お電話からお気軽にご連絡ください。
ネット予約・お問い合わせは24時間承っております。