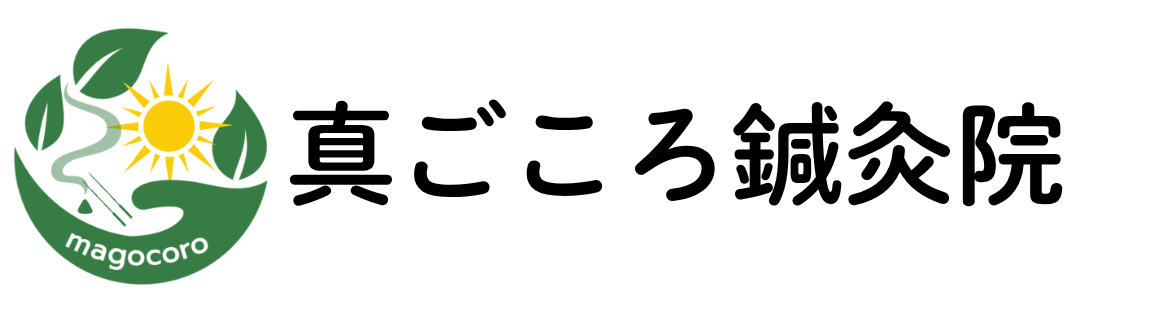右肩の痛み(五十肩)

 これまでの経過
これまでの経過
約4ヵ月前から急に右肩が痛くなった。
右肩を前と横から90°位に挙げた時に、肩の後ろ側が痛む。
病院のレントゲンでは骨に異常無し。
靭帯も異常は無く、五十肩と診断された。
 鍼灸院としての診断
鍼灸院としての診断
考えられる原因①血液の循環不良
まず東洋医学では「不通促通(ふつうそくつう)」という考えがあり、主に「血液の巡りが悪くなると痛みが出る」という意味です。
今回の肩の痛みも、体の血流が悪くなっていることが原因の1つです。
考えられる原因②経絡(けいらく)の滞り
東洋医学では人体には360個以上の経穴(ツボ)が存在していると考え、経穴を結んだ線を経絡と呼びます。
経絡には体のエネルギーや栄養素を示す「気・血・水」が流れています。
痛みが出ている肩の後ろ側には「手の少陽三焦経」と「手の太陽小腸経」という経絡が通っています。
これらの経絡が滞ると痛みなどの症状が出るので、「肩の後ろ側に流れている経絡の滞り」も原因の1つと考えられます。
 治療方針
治療方針
①血液の循環不良
②経絡の滞り
を解消する治療を行いました。
①血液の循環不良に対しては、東洋医学では五臓「肝・心・脾・肺・腎」の働きを診て施術を行い、五臓の中で「肝」が体の必要な場所に血液を送り届ける役割があります。
なので、肝の働きが眼精疲労、寝不足、イライラ、過度な飲酒、多忙などで弱くなると、体の血液循環が悪くなり、痛みが出やすい体になってしまうので、肝の働きを高める施術を行いました。
②経絡の滞りに対しては、
「手の少陽三焦経」は手薬指→腕後面中央→肩後面へと流れ、
「手の太陽小腸経」は手小指→腕後面外側→肩後面へと流れているので、それぞれの内臓に属すツボを使用し、それらの経絡を疎通させる目的でアプローチしました。
 治療内容
治療内容

・中封(ちゅうほう)
・肝兪(かんゆ)
・太衝(たいしょう)
などの肝のツボ
・後谿(こうけい)
・外関(がいかん)
など小腸経と三焦経のツボに鍼やお灸を行いました。
また、痛みが出ている右肩周りに鍼を数ミリ刺したまま肩を動かす「運動鍼」という治療法で局所の血流をより促す施術も行いました。
 施術回数・頻度・期間
施術回数・頻度・期間
1週間に1回の治療を行いました。
1回の治療:治療後3日間は調子良かったが戻った。
5回の治療:朝の痛みが軽くなった。
9回の治療:腕を前から約180°上げられるようになった。
21回の治療:腕を横から約170°上がるようになった。
24回の治療:肩の可動域が正常となり、痛み無し。
治療終了。
まとめ
五十肩は治療期間が長くかかる傾向があります。
なぜなら、痛みや可動域制限などで肩が動かせなくなることで血液の巡りがよくなりにくいからです。
改善を少しずつですが痛みの強さや痛みを感じる頻度も減っていきますので、辛抱強く治療をしていきましょう。
私もなるべく早く症状を改善出来るように、日々精進します。