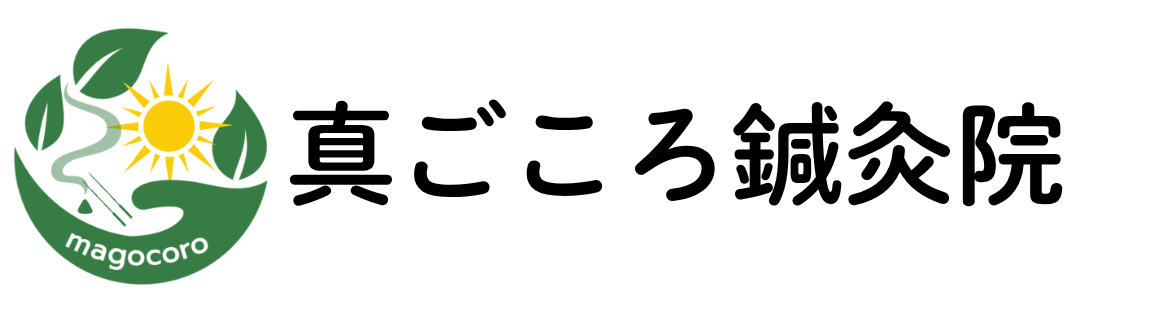手足の多汗症

これまでの経過
小学生くらいから手のひらと足の裏に汗をかきやすい。
仕事で人と握手をする機会が増えて、気になるようになった。
皮膚科で処方された汗を抑える薬をつけている間は汗はひくが、とれてくると汗が出てくる。
治療方針
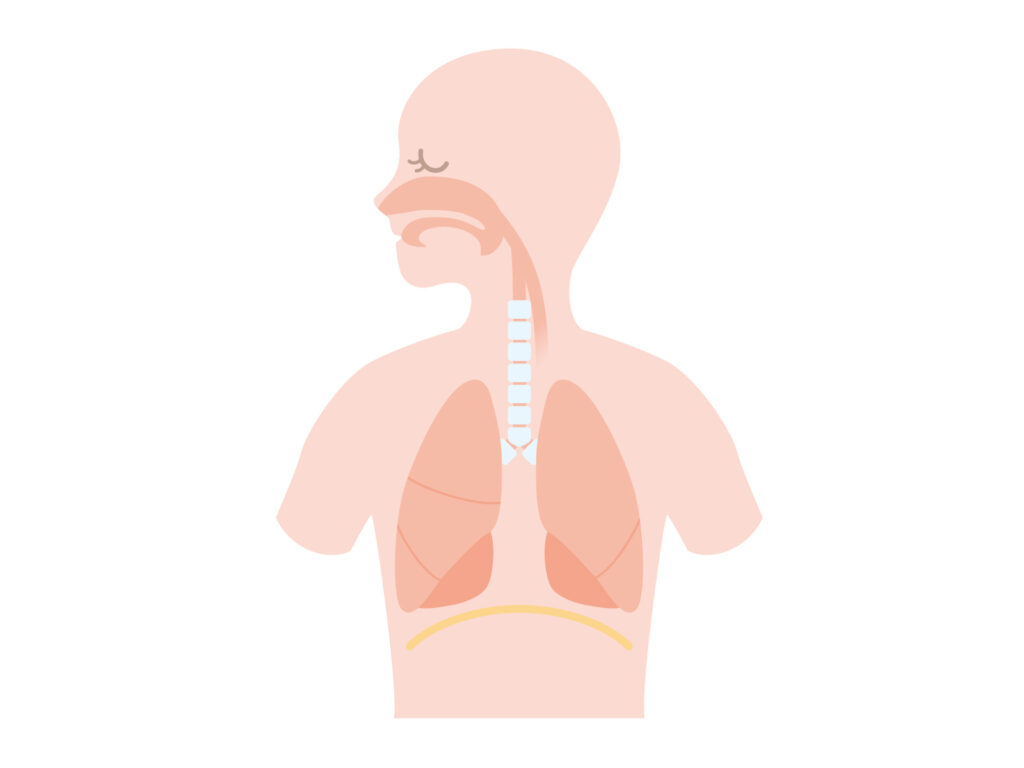
東洋医学では五臓六腑の中の「肺」が「汗」と関係しています。
肺は外から体内に入り悪さをするもの(ウイルス、寒さ、暑さなど)を入れないバリアとして皮膚表面に気を巡らせています。
肺の働きが低下するとバリアがなくなり毛穴が開き、汗が出ると考えています。
ですので、手や足から汗が多く出るのは肺の働きが弱くなったことが原因で毛穴が開いていることが原因なので、肺の働きを高める治療をすると段々と汗の量が減っていきます。
治療内容

肺のツボを使用し、肺の働きを高める治療を行いました。
・太淵(たいえん)
・肺兪(はいゆ)
など
また、体表のバリアとして巡っている気を補う為に、「気」という文字がついたツボにも鍼やお灸をしました。
・気衝(きしょう)
・気海(きかい)
施術回数・頻度・期間
1週間に1回の治療を行いました。
1回の治療で汗が半分位まで減る。
5回の治療で汗が7割減る。
8回の治療で汗が9割減る。
9回の治療でほぼ気にならない。
治療終了。
施術後のケア
病院では交感神経をブロックして汗を止める薬や注射、汗を出している神経を取り除く手術などが行われますが、薬や注射は汗が出ない様に症状を抑えているだけなので、効き目が切れたらまた汗は出てきてしまいます。
発汗をコントロールする神経を遮断する手術では、代償性発汗のリスクがあります。
代償性発汗とは、手術によって発汗が抑えられた部位以外の場所(例えば背中、腹部など)で、異常な発汗を生じる現象です。
当院が行う鍼灸治療では西洋医学(病院で行っている治療)のような副作用はなく、体質を変える為継続して治療を行う必要がありますが、安全な治療だと言えます。
多汗症でお困りの方は鍼灸治療(東洋医学)を検討されることをおススメします。