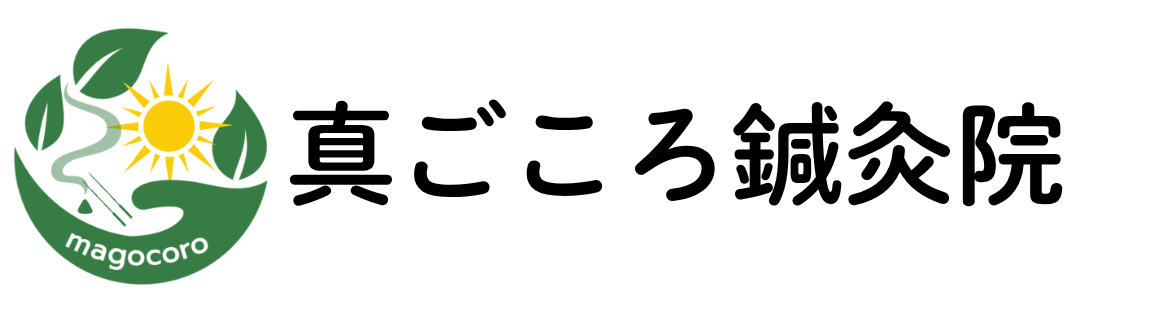こんなお悩みは
ありませんか?
病院でよくある対応
非定型歯痛(原因がはっきりしないのに歯や周囲が痛む状態)は、西洋医学の現場でも対応が難しい症状のひとつです。
原因が分からないので抗うつ薬・抗てんかん薬、抗不安薬などを処方され、心療内科受診を勧められる場合が多いです。
しかし、病院や心療内科で一通りの治療を受けても改善が見られない場合もあります。
- 痛みが長引くことで、日常生活や食事の楽しみが制限され、気持ちが落ち込む。
- 不要な歯の治療や抜歯を受けてしまい、「本当にこれでよかったのか?」と考える。
- 周囲から理解されにくく、「気のせいでは?」と言われてしまうことで、孤独を感じる。
そんなお悩みを抱えている方も少なくありません。
なぜ病院では改善できないのか?
非定型歯痛は、歯が原因ではないのに歯やその周りが痛む病気です。
そのため、ふつうの虫歯や歯周病と違って、病院で調べても「異常なし」と言われることが多いのです。
実際には「神経の過敏」や「脳での痛みの感じ方の異常」が関係していることが多いため、病院では対応しきれません。
一方、東洋医学では「腎」が歯や骨を支配すると考えるため、腎が弱ると歯や顎のトラブルが出やすくなります。
「腎の力」は 生まれたときに親から受け継ぐもの が一番強いと考えられており、
子どもが成長すると歯が生え変わるのも、年をとると歯が弱くなるのも、腎の働きと深くつながっている、と東洋医学では説明します。
体の健康を支える基本的な3つの要素の「気血水(き・けつ・すい)」のバランスが乱れると、非定型歯痛のような痛みや不調も出やすくなります。
東洋医学の治療では、その人の体質を見極めてバランスを整えることで、痛みの改善を目指します。
東洋医学とは?
東洋医学とは体の巡りやバランスを整えて自然に治る力を引き出す医学です。
体の中には、
- 気(エネルギー)…体を動かす力
- 血(栄養や潤い)…全身に栄養を運ぶ
- 水(体の水分や体液)…血液以外の水分の循環を助ける
が巡っており、これらを総称して「気血水」と呼びます。
気血水の流れが滞ったり不足したりすると、歯の不調や体の症状が現れやすくなります。
また、東洋医学では五臓六腑という考え方があります。
- 五臓(肝・心・脾・肺・腎)は体の大事な働きをまとめて管理する臓器
- 六腑(胆・胃・小腸・大腸・膀胱・三焦)は食べ物や水分の消化・吸収・排泄を担当
鍼灸治療で気血水の巡りと五臓六腑のバランスを整えることで体の回復力を引き出し、症状の改善が期待できます。
非定型歯痛になりやすい
3つのタイプ
腎の力が弱いタイプ
腎は歯や骨を支えるため、腎が弱くなると歯のトラブルが起こりやすいです。
腎の働きが弱くなると
- 腰や膝がだるい
- 疲れやすい
- 耳鳴りや物忘れがある
などの不調が起こりやすいことが特徴です。
気の巡りが滞りやすいタイプ
気の流れが悪くなると、痛みが出やすくなります。
気の巡りが滞ると
- ストレスや緊張を感じる
- 肩こりや頭痛がある
- イライラしやすい
などの不調が起こりやすいことが特徴です。
血の巡りが悪いタイプ
巡りが悪いことで、歯や顎の痛みが取れにくくなります。
- 顔や手足がむくみやすい
- 頭重感がある
- 食欲不振、胃もたれがある
などの不調を起こりやすいことが特徴です。
東洋医学的なアプローチ
東洋医学では鍼(はり)やお灸でツボを刺激し内臓の働きを高め、
気血水の巡りを良くすることで歯や歯の周りの組織に十分な血流と栄養が届くようにサポートします。
- 太谿(たいけい)
腎を補い、歯や骨を支える力を強める。
- 太衝(たいしょう)
気の流れをスムーズにして緊張を緩める。
- 三陰交(さんいんこう)
血を補い、全身に栄養を巡らせる。
まとめ
非定型歯痛は「歯だけを治療しても改善しにくい」ことが多いですが、
局所+全身のツボを組み合わせて内臓の働きを高めたり、気血水の流れを整えることで、痛みをやわらげ、慢性化を防ぐことができます。
非定型歯痛やそのような症状でお悩みの方は是非ご相談下さい。
実際に非定型歯痛が
改善した例

お問合せ・ご予約
当院は完全予約制です。
ご予約は公式LINE, しんきゅうコンパス, お問い合わせフォーム, お電話にて承っております。
お問い合わせはお問い合わせフォーム, お電話からお気軽にご連絡ください。
ネット予約・お問い合わせは24時間承っております。